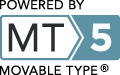のっけからの出題で恐縮ですが問題を出しますので考えてみてください。
「間合いとは何か、述べよ」
えっ?なに?禅問答…?いやそうじゃなくて剣道の昇段審査なんです。これとあと一問が出題され、制限時間の20分以内にA4の解答用紙に記入するんです。
6月22日、剣道の昇段審査というのに行ってきました。初段~三段までの審査が行われた。自分の場合そもそも有段者ではないから昇段ではなく何ていうんだろう?入段?んーーなんか語感が悪いな…。やっぱ、昇段なんだろうか…?それはともかく、剣道の初段は一級をもっていないと受審することができないのでこの前5月19日に一級を受験しにいったばかりだったのだ。
私の剣道経験といえば高校の時の体育の授業で素振りや防具をつけて面打ちとかの基本的なことはやったことはあったものの、もう何十年も前の話でほとんど初めて剣道をやっているのと同じなのだ。まあ、大人になってから剣道を始めたオジさんが段審査を受けに行ったというスタンスで読んで欲しい。ちなみに防具をつけて稽古するようになって1年半ぐらいです(といっても週に2回ほどだが)。
自分が行ったのは広島県西地区剣道連盟の昇段審査会だ。廿日市市にある広島看護大学の体育館を借りて審査会が行われた。建物はまだ新しくとても綺麗な会場である。初段を受験する受験者は82名(自分がその一番後ろの番号…年齢順だから)二段と三段がそれぞれ15~20人くらいずついた。初段を受けるのはほとんどが中学生で、高校生らしきのが一名、一般の人が自分を含めて二名だった。二段、三段となると一般の人も多い。ちなみに初段を受ける資格があるのはまず剣道一級取得後、修行一ヶ月以上かつ、中学二年生以上のものとなっている。(これは全国ともそうなのか私は知らない)要するに一般の人なら一級取得後一ヶ月後には初段の受験資格ができるということである。
ちなみに剣道の段はその受験資格が結構厳しい。剣道が強ければどんどん上に上がっていけるわけではないのだ。例えば二段を受験できるのは初段取得後一年後、二段だと二年後、三段だと三年後…というふうに段数と同じだけ修行を積まねば、審査を受けることすらできないのである。小学校から始めても七段を取得しようと思うと最短でも30歳は軽く超えてしまうのだ。私は将棋の有段者(初段)でもあるが将棋の場合は実力があればいきなり四段が取得できるから剣道の場合はいかに厳しいかがわかるだろう。
さて、この審査会一体どんな段取りで進むのか?
1)実技
2)昼食
3)剣道形
4)筆記試験
ぬあに?筆記試験?剣道の審査には筆記試験があるのか?そうなんです。冒頭に問題を書いたように筆記試験があるんですよ。まずはビックリしたところで詳細はまた後で述べるとしよう。
審査するのは高段者の先生方5名でその他にも審査委員長という先生が少し離れたところで審査されるのだ。
まず実技試験。5名がグループとなってそのうち2名の人と対戦する。これは試合ではないので勝ち負けは関係ない。審査員の先生方は剣道の基本、構え、気勢そういったところを見ているので小手先で勝負に走ってもダメなのだ。例えば「始め」の合図でいきなり後ろに下がるとか、相手が打ってくるのを待ってその対応だけするとかそういう剣道では不合格になってしまう。勝ち負けは関係ないとはいうものの、やはり有効打突(いわゆるメンとかコテとかいうやつ…)は必要でしょう。段位が上がれば審査する目も厳しくなってくるでしょう、たぶん…(^^;昼食休憩の途中でここまでの実技審査での合格者が発表された。
剣道形というのは木刀を使って決まった形を「打ち太刀」「仕太刀」の二名のペアに分かれて演舞するのだ。これは全部で10種類(10本という)あって、初段の場合は一本目~三本目まで二段は同五本目まで、三段は同七本目まで行う。前の週に一応これの講習会というのがあってほとんどの人は受講しているはずだが普段から練習してないと(^^;なかなかうまくできないのだ。自分の場合は前の週から一緒に受講、受審していた一般の人が相手になって審査に臨むことになるだろうと思っていた。事実、実技審査が終わったあとその時点での初段の部合格者は偶数だったから受験番号82番の私は当然81番の一般の人とやることになると思っていた。番号の若い順に打ち太刀、仕太刀と割り当てていくと私は仕太刀になる。自分の場合仕太刀の方がやりやすいのでここで一安心していた。81番の人も打ち太刀の方がやりやすいということだったので良かったですね。といいながら昼休みにお互いを相手として練習した。
さて実際の剣道形審査が始まって整列を始めると…あれれ?一人づつずれてるぞ。81番の人は仕太刀になってしまって慌てているし、82番の私も打ち太刀になってしまった。おかしいなと思って隣を見ると女子の部が奇数なのだ。そうかここまでの初段の部合格者は全体では偶数だが女子が奇数、男子が奇数、両方で偶数ということだったのだ。打ち太刀になってしまうのはまあ仕方ないとしてもっと困ったことが起こった。最終番号の私には相手が居なくなってしまったのだ。
段取りをしている係の人がやってきて「どうしますか?」えっ?どうしますかって言われても相手がいないことにはどうしようもないじゃんと思っていると「だれかやりやすい人を指定してもらっていいですよ。」え?そうなの?幸い初段の部にはいつも一緒に稽古している中二の翔君が受験にきている。「じゃあ、57番の子を相手にお願いします。」翔君は2回実技することになり悪いと思ったが、まあ彼の場合は大丈夫だろう。打ち太刀の三本目には足の送り方にちょっと難しいところがあるのだが何とかクリアできた(^^)
さて、その剣道形審査をクリアすると最後は筆記試験だ。今年度は冒頭に書いた問題ともう一問が出題された。「間合いについて述べよ」と「剣道修行の目的と効果について述べよ」である。
いきなりこんな問題を出され答えよと言われても大人でも20分という短時間に答えられるものではないだろう。しかも初段受験者のほとんどは中学生である。ナニ?中学生の方が勉強では現役だからそっちの方が有利?なるほど…。実際のところは前の週の昇段講習会でポイントが解説されており、ちゃんと解説書も存在するから要するにポイントを覚えておけばたいてい大丈夫ではある。しかし、今回の審査会では3名も筆記試験で不合格となっている。実技->剣道形審査->筆記試験までやると夕方前ぐらいまでにはなっている。筆記試験で不合格ともなるとガックリくるだろう。ちゃんと勉強してから来ようね(^^; …って私の場合はここんとこ仕事が度を過ぎて忙しく毎日深夜まで及んでいたためそれどころではなく、解説書を開いたのは前日だったのだ…。
というわけで長い一日が終わったのだった。自分の場合はここ1ヶ月は仕事の関係でほとんど稽古も準備もできず、ぶっつけ本番のような形になってしまったが何とか合格できてほっとしたというのが正直な感想です。来年は二段に挑戦する予定なので、こんどはちゃんと準備万端の態勢で臨みたい…。